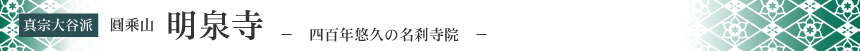- 連載トップページ>
- 劫火の中になお生命ありて その4
「劫火の中になお生命ありて」
円乗山明泉寺14世住職:水谷光子
劫火の中になお生命ありて その4
二日ほどして、隣家の焼け跡から、母と弟の焼死体が見付かった。二人の生存を期待していた私は、変わり果てた母と弟の姿に、心身の力が一時にすっかり抜けていくのを感じた。隣家のご主人も、少し離れた所で、亡くなられていた。弟を水風呂に入れて、母は弟を庇う形で亡くなっていた。風呂桶は焼き尽くされ、残されたたがが、弟の体を巻いていた。水に浸っていたから、弟の体は余り焼けず、入学したばかりの静中(現・静岡高校)の帽子の徽章が、傍らに残されていた。母は實に無惨な焼死体だった。和服式のモンペを着ていたが、重ね合わさった襟元が僅かに残り、その柄で辛うじて母と判別できたのであった。
坪庭の一隅に、祖父・母・弟の遺体を安置し、町内の防衛団の方々のお力添えで、荼毘に付したのは、四日後の夕刻だった。あちこちから寄せ集めた、焼け残りの柱などの木片を使っての火葬である。駆け付けてくださった総代の小島さんに付き添われ、私は喪主として点火し、ひたすら正信偈を誦した。この時、私が暗記していたお経は、他になかったし、火葬や葬式にどのお経をあげるかなども、全く知らなかったのである。三人の家族と今生での袂別である。精一ぱい、お経をあげようと思いつつも、声は涙に途切れ胸はうつろ、半ば虚脱状態だったようである。劫火の中での正信偈と違って、あのときの落ち着きはなく、乱れに乱れたお勤めしかできなかった。どこかで生きている筈の父の身も案じられるし、重度の火傷で身動きの儘ならぬ妹には、未だ話しそびれているし・・・。遺体は六月のこと、四日も経っているから、鼻を突く異臭だった筈だが、そんな記憶は全くない。焼け跡の強烈な臭いに消されたのだろう。めらめらと上がる炎は、あの空襲の日の炎と違って、限りなく清浄な炎に思われた。多感な青春の感傷であったのか・・・。私はひたすら念仏しつつ、その炎に見入っていた。そのうちに、ふとこの浄らかな火に飛び込み、母と一緒に、彼の国へ旅立ちたい衝動に駆られた。勿論それはほんの一瞬のことで、すぐ我に返った。重傷の妹と、どこかで生きている筈の父への責任である。あの劫火の直中にあって、なおも生かされた生命である。『生かされたからにはそれだけの使命がある』と気付いたのは、荼毘の中に母の声を聞いたような気もする。
兵隊さんの担架に委ねた父の行方は、その後八方に手を尽くしたが、杳として判らない。病院まで辿り付けたか否か。とにかく、何処かで生命を終り、傍らに肉親がいなかったので、多分身元不明人として、遺体を処理されたのであろう。今でも私は、父に詫び続けている。けれどもあの場合、どうしたらよかったのか。父は何を望んだ筈か。考えても考えても、答えが出ない。父と妹を同時に、同場所に運んで貰えなかった不運を思う。よく頼んだのに、聞いて貰えなかったのだが、あの兵隊さんにも、如何にもならなかった状況が、充分理解できるから何も言えない。後日合同で火葬された身元不明者の、遺骨の一部を引き取らせて戴き、父のお骨として納骨した。存命なら既に百歳を越している。しかし私の胸には、五十歳の若々しい父の面影が、今も生き続け、ごく僅かながら、再会への期待さえまだ消えてはいないのである。